★重要なお知らせ 2024年4月1日より、「レイバーネットブッククラブ」の情報提供は「レイバーネットサブチャンネル」に移行しました。今後はそちらを参照してください。なお、このサイトは以前のアーカイブとして残しておきます。移行サイトは https://www.labornetjp2.org/specialized/book-club/ です。
第47回読書会報告『アンブレイカブル』(柳広司)(2024/4/6)

ブッククラブの志真秀弘です。 次回(47回)読書会は4月6日(土)午後2時開会です。 『アンブレイカブル』(柳広司著、角川文庫、780円)を取り上げます。 ◯日時:4月6日(土)午後2時から4時まで。 オンライン参加とし、Zoomを使いますが、ビデオプレスにて、リアル参加も可能です。ビ デオプレス地図↓ http://vpress.la.coocan.jp/map.html ◯テキストは、『アンブレイカブル』(柳広司著、角川文庫、780円、24年1月刊)です。 久方ぶりに小説をテキストにします。小説は19年4月(15回)に『82年生まれキム・ジヨ ン』(チョ・ナムジュ)を取り上げて以来です。 今回の『アンブレイカブル』は四話からなる連作短編小説集。小林多喜二、鶴彬、横浜事 件の犠牲者、そして三木清がそれぞれの主人公。そしてもう一人、全編を通して登場する のが内務官僚クロサキ。 アンブレイカブル(敗れざるものたち)は、冬の時代に屈することなく、どのように生き たかが鮮やかに描かれています。冒頭の第一話「雲雀」は、銀行員時代の多喜二の快活な 日常が浮かび、そしてミステリアスなエピソードが絡み、本を閉じることができません。 多喜二の豊かな人間性が行間からたち上がります。謎の行方を追いながら、時代の嵐に抵 抗した人々の息吹を感じる無二の小説集です。 ぜひご参加ください。
◯参加要領 ①参加希望の方は、開会前日までに「〇〇です。読書会に参加します」と書いて下記あて メール送信してください。 mgg01231@nifty.ne.jp ②申し込みいただいた方には、開催前に案内メールを差し上げます。
第46回読書会報告『イスラエル軍元兵士が語る非戦論』(2024/2/18)

2月18日(土)、第46回ブッククラブ読書会が開かれました。取り上げた本は『イスラエ
ル軍元兵士が語る非戦論』(ダニー・ネフセタイ著、永尾俊彦構成、
集英社新書)。参加者は11人でした。そのうち2人はビデオプレス事務所での参加でした。
著者のネフセタイさんは本書発行後、各地でトークイベントを展開していて、それに参加
された方もいました。
いまガザではジェノサイドと呼ぶほかない事態が進行しています。その渦中での読書会で
したので、討論は、おのずとそれに関わるものにもなりました。
本書のはじめに、イスラエル国内の学校教育の実情が紹介されています。軍隊への憧れを
養い、「国のために死ぬのはすばらしい」と言う感情を培う「平和教育」と聞くと、日本
はそれとかけ離れた現状だとは言い切れないとの意見が多くありました。本書は空軍兵士
であり、若い時代をイスラエルで過ごした著者の体験が踏まえられているので具体的で、
説得力がある。大戦中のホロコーストからイスラエル建国、そして現在に至る歴史過程も
、本書は的確にまとめていて、わかりやすい。イスラエルの戦争を肯定する立場から、非
戦を主張する考えへと、著者はどのように自己変革したか。本書は、その記録でもあるで
しょう。この本は、パレスチナ問題を考える基本の書だとの評価で一致しました。
さらにガザの現在に触れて、そしてウクライナの今にも関連して、反戦平和の意見と行動
をどう広げていくか、幾つも意見がありました。戦争の危機、それに対する平和への行動を、参加者一人ひとりが、切迫した課題と捉えていることが強く伝わる討論でした。
なお次回は4月6日(土曜日)午後2時から、今回と同じくオンラインとリアルで開催します。
●第45回報告『検証 ナチスは「良いこと」もしたのか?』(2023/12/10)

志真秀弘です。
12月10日(日)ブッククラブ読書会(45回)が開かれた。参加者は10人(そのうち二人の方がビデオプレス事務所から参加された)。
取り上げた本は『検証 ナチスは「良いこと」もしたのか』(小野寺拓也・田野大輔、岩波ブックレット、820円)。
この本は「週刊本の発見」(10月15日)で大西赤人さんが「『インフルエンサー』世論の危うさ」として取り上げ、現在のネット状況の危険性も指摘しています。TBSラジオに著者二人が出演し、本も刷りを重ねているようです。ナチス登場の歴史過程と現在のそれを肯定的に捉えるような議論への危機感とで活発な討論になりました。
ヒトラーの政権掌握の歴史的プロセスなど、本書は歴史研究の成果を活かして丁寧に解き明かしている。
討論では、そこがまず役に立つとの意見が共通して出された。ナチスは権力を握ったのち、歓喜力行団をはじめ巧みな宣伝と組織化で人々をとらえていったこと。その背景に経済危機とそれによる排外主義とがあり、現在の状況との類似性も語られた。権力への沈黙と同意にみられる社会心理的動向にも注目したいとの意見もあった。今の歴史修正主義の実態を見ると、歴史教育の現状も考えないわけにはいかない。たとえば参政党などは環境保護の主張でカモフラージュしながら、その実、正真正銘の排外主義を主張するなど、歴史の教え方の弱点をついてきている。
本書のいう歴史の見方を育てる基本―〈事実〉〈解釈〉〈意見〉という三層に分けて考えていくことはとても大切であり、念頭におきたいとの感想が多くありました。また日本とドイツとの近代化の歴史的差異、特に日本では「天皇を天皇にしていった過程にある権威主義」、戦争責任追及が弱かった点なども改めて考えたい。
●第44回読書会報告: 『コモンの「自治」論』(2023/10/21)

10月21日(土)ブッククラブ第44回読書会が開かれた。
今回取り上げた本は『コモンの「自治」論』(斎藤幸平+松本卓也編、集英社)。
参加者は7人。討論後に参加できなかったけれど録画を送ってほしいとの声(今のと
ころ6人)が寄せられたが、これだけの方から要望のあったのは初めてで、本も討論も注
目されていることを感じた。
討論は、「読んでいて嬉しい」「どの書き手も実践例を豊富に紹介していて、とても刺激
を受けた」などの感想から始まった。
地域の中で議論のできる仲間を作ることの重要性、そして同時にその難しさも語られた。
岸本聡子・杉並区長は第3
章で「自治」とは暮らしの未来を考える行為だ、〈地方自治こそがカギ〉と強調して、幾
つもの手立てを紹介している。さらに「市民科学が場をつくる」(木村あや)、「独立自
営業という希望」(松村圭一郎)などの提言もおもしろい、との声も多かった。
「大学における自治の危機」(白井聡)をめぐって、当時の運動が学生に限られたことに
弱点があった。行ってみると早稲田大学にあった二つの学生会館も無くなり、古本屋街か
ら社会科学の本は消えてしまい、大学が無菌室のようになってしまっている。そんな状態でも議論を続けることで運動の可能性を開いていこう、それが若い世代に繋がることになるというのが参加者の総意だった。
次回は12月10日(日)開催予定です。希望の本がありましたらお知らせください。→メール
●第43回読書会案内: 『朝のあかりー石垣りんエッセイ集』(2023/8/26)

次回43回読書会は8月26日(土)午後2時開会です。 今回は、『朝のあかりー石垣りんエッセイ集』(中公文庫、2023年、900円)を取り上げ ます。石垣りんの詩は戦後詩を語るとき欠かすことはできません。 石垣は1920年東京生まれで2004年に亡くなっています。高等小学校卒業後14 歳で日本興業銀行に事務見習いとして就職、定年まで家族の生活を支え続けました。敗戦 後組合活動に参加しながら詩作に集中し、エッセイも多く書いています。 ◯日時:8月26日(土)午後2時から4時まで、
オンライン参加とし、Zoomを使いますが、ビデオプレスにて、リアル参加も可能です。ビ デオプレス地図↓ http://vpress.la.coocan.jp/map.html ◯テキストは『朝のあかりー石垣りんエッセイ集』(中公文庫、900円))です。 「そのころ、女性の地位は極端に低かった。封建社会になぞらえるなら武士と町人のへだ たり、階級がまるで違う扱い。女性は親睦会に入会することも出来なければ、寮の使用も ゆるされず職場結婚などもっての外であった。」 これは「良い顔と幸福」と題された文章からの抜粋です。働くことと生活とを詩人の眼で 見つめた心にしみ込む文章が、本書にはならんでいます。解説は梯玖美子。 なお『石垣りん詩集』(伊藤比呂美編、岩波文庫、2015年刊、814円)が出ています。 ◯参加要領 ①参加希望の方は、開会前日までに「〇〇です。ブッククラブに参加します」と書いて下 記あてメール送信してください。 mgg01231@nifty.ne.jp ②申し込みいただいた方には、開催前にあらかじめ案内メールを差し上げます。
●第42回読書会報告: 岸本聡子『地域主権という希望』(2023/6/10)

6月10日(土)第42回レイバーブッククラブ読書会が開かれました。参加者は7人でした。取り上げた本は岸本聡子・杉並区長の『地域主権という希望―欧州から杉並へ、恐れぬ自治体の挑戦』(大月書店)です。
討論ではヨーロッパでミュニシュパリズム(地域主権主義)が広がりを見せていることに驚くとの意見がほとんどだった。現代社会の抱えている問題にこの主張はほとんど対応している。日本では、あるいは杉並以外ではこうした活動はなかなか広がらない現状がある。が、「著者のような人が現れたということ自体が希望なのだと思う」。また「ミュニシュパリズム」というカタカナ語は舌を噛みそうで抵抗を感じる、広げるためにも「適切な訳語を」、という意見があり、差し当たり地域主権主義あるいは自治体主義などでどうだろうかとの意見があった。
他方、僅差とはいえ著者を区長に選んだ杉並区住民の歴史的な力、「ひとり街宣」をはじめ対話を主調にした選挙活動の工夫などが素晴らしかった。こうした議論のなかで誰にとっても、いま職場はもちろん地域でも「居場所」がないという切実な問題が指摘された。入管法闘争の現地(愛知)の参加者の声からもそれは感じられた。
ただ入管法闘争では参加者に若い人も多く、なかでも女子学生の多いことに希望が感じられたという。正義感、人権感覚は崩された教育状況の渦中にあっても崩壊してはいない、その意味でオンラインも含めて「いろいろな場所作り」は大切だろう。
▷次回は8月26日(土)午後2時開始。オンラインとリアル(ビデオプレス事務所)とのハイブリッドで行います。
とり上げる本は未定ですが、決まりしだい案内します。またこの本を読みたいという希望をぜひお寄せください。
●第41回読書会報告 : 小田実『「難死」の思想』(2023/4/9)
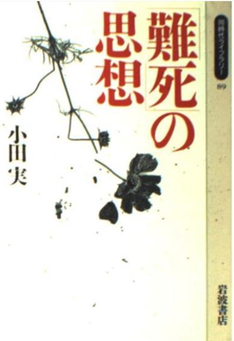
4月9日(土)、第41回ブッククラブ読書会が開かれました。取り上げた本は『「難死」の思想』(小田実、岩波現代文庫)。参加者は10人でした。
小田実の著書は『何でも見てやろう』以来初めてという人が多かったのが今回の特徴だった。かれの「かれ流の言葉を作る」方法は、出来合いの言葉で安直に語らないことからきている。さらに行動との絡み合いのなかで言葉の普遍性が高められていく。
1965年から75年にかけての10年間―戦後日本があっという間に経済成長の波に飲み込まれていく時代に、市民運動は何を志向し、何を考えていたかが本書を読むとよくわかるという声もあった。
小田は歩きながら考えていく人だ。きちんと整理されたところではなく、はみ出したところから考えている。それが、自分自身が加害の問題、植民地主義の問題を考えてこなかったという反省に通じていく。
また、ベ平連(ベトナムに平和を!市民連合)に早い時期から参加した経験も語られた。小田の「人間みんなちょぼちょぼや」という言葉を噛み締めて、運動のなかにえらい人を作らない、弁護士や大学教授を「先生」と呼ぶことはやめようと主張してきた。
また小田の非暴力の主張は沖縄の闘いーたとえば阿波根昌鴻さんの反基地闘争に学んだものだ。またかれ自身かつての日本社会党の「非武装中立」の思想を高く評価していた。
こうして本書は今日に通ずる問題を先駆的にとらえていて、それが活発な論議を呼んだ。
▷次回は6月10日(土)午後2時開始。オンラインとリアル(ビデオプレス事務所)とのハイブリッドで行います。
読む本はまだ決まっていません。決まり次第ご案内します。読みたい本がありましたらぜひご投稿ください。(志真秀弘)
●第40回読書会報告 : 『ルポ 食が壊れる』(2023/2/4)
2月4日(土)第40回ブッククラブ読書会が開かれました。取り上げた本は『ルポ 食が壊れる』(堤 未果、文春新書)。参加者は10人でした。
本書前半は、GAFAに象徴される巨大資本の支配が身近な食べ物にまで及び、遺伝子組み換えから人造肉にまで進んでいることをいくつもの事例をあげて説明している。文字通り〈神の領域〉まで、そして人間の命に関わる領域を資本主義が侵そうとしていることがよくわかる。利潤追求の自己運動は際限がない。ナオミ・クラインの「惨事便乗型資本主義」を想起した。同時に、本書は後半でこれに抗う民衆の抵抗を国内はもちろん世界的な視野から捉えている。討論でも有機農業について協同組合や学校給食との連携のあり方など活動に参加した経験が話された。ブラジルのルラ政権の政策についても本書は紹介しているが、そうした国際的な経験にも希望を見出すことができる。他方、最近の参政党などの教育と食と国家防衛を絡めた「有機農業」の提唱に潜む危険性にも討論は及んだ。ナチスの歴史を検証する必要も指摘された。(藤原辰史『ナチス・ドイツの有機農業』(柏書房)は、そこを分析したすぐれた仕事のようですー志真記)
本書は大資本の最新の動向を捉え、さらに民衆のこれへの抵抗を実例を挙げて探っている優れたルポルタージュであり、それが討論の熱量を高めたようです。
▷次回は4月9日(日)午後2時開始。オンラインとリアル(ビデオプレス事務所)とのハイブリッドで行います。
取り上げる本は『難死の思想』(小田実、岩波現代文庫、1300円)です。1960年代半ばから70年代半ばにかけて発表された小田実の文章をまとめたもの。今世紀初頭の原発事故、疫病の蔓延、そして戦争。民衆が死に追いやられている今、改めて読み直したい本です。(志真秀弘)
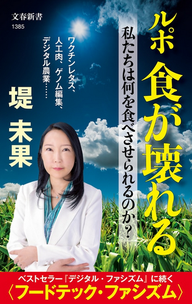
次回読書会のお知らせ ブッククラブの志真秀弘です 〈レイバーブッククラブ〉第40回読書会は2月4日(土曜日)。今回は、堤未果『ルポ 食が壊れる』を取り上げます。 ◯日時:2月4日(土)午後2時から4時まで、 オンライン参加とし、Zoomを使いますが、ビデオプレスにて、リアル参加も可能です。地 図↓ http://vpress.la.coocan.jp/map.html ◯テキストは『ルポ 食が壊れる 私たちは何を食べさせられるのか?』(堤 未果、文春新 書、2022年12月刊、900円)です。 USA系巨大企業による農業分野への進出はすで1 世紀以上の歴史を持ち、破壊は世界各地に及ぶ。それがここに至って、人造肉の製造をは じめ食品そのものまで変えられようとしている。 2020年6月世界経済フォーラム(WEF) は、コロナウィルス、気候変動、人口増大などの危機に対して〈グレートリセット〉の方 針を発表した。億万長者と有力者の唱える食料システムーそこに問題のないはずはない。 ゲノム編集のテクノロジーによって、農業から食品産業まで巨大企業の利益本位に全てを 転換する企みが始まっている。 本書は農と食における破壊の実態をレポートし、さらにアグリビジネスの野蛮な攻撃に対 する抵抗の活動も伝える。 本書の取材執筆には4年の歳月を要したと書かれている。 新書というコンパクトな作りにも関わらず、問題の全体像―農と食における破壊と抵抗の 実態が的確に伝えられる。 農と食の危機を考えるためにも、ぜひ読んでご参加ください ◯参加要領 ①参加希望の方は、開会前日までに「〇〇です。ブッククラブに参加します」と書いて下 mgg01231@nifty.ne.jp ②申し込みいただいた方には、開催前にあらかじめ案内メールを差し上げます。
●レイバーブッククラブ 読書会記録(2017-2022)
以下は2017年に始まったレイバーブッククラブの記録です。ここから〈いま〉という時代の断面もみえてくるようです。
新年2月4日は第40回(オンライン)。後日ご案内します。(2022.12.20 しま)
********
レイバーブッククラブ 読書会記録
① 2017.7.5 「洛東江」趙明煕(岩波文庫『朝鮮短編小説選(上)』)所収
② 9.17 『沖縄を生きるということ』(鹿野政直・新城郁夫、岩波書店)
③ 10.15『キジムナーkids』(上原正三、現代書館)
④ 11.19『労働者階級の反乱』(ブレイディみかこ、光文社新書)
⑤ 12.24『パパラギ』(エーリッヒ・ジョイルマン、S B文庫)
⑥ 2018.1.27『日本のフェミニズム』(北原みのり ほか、河出書房新社)
⑦ 3.3 『新・日本の階級社会』(橋本健二、講談社現代新書)
⑧ 4.14『ガンジーの危険な平和憲法案』(C・ダグラス・スミス、集英社新書)
⑨ 5.12『水田まりのわだかまり』(宮崎誉子、新潮社)
⑩ 7.15『原発労働者』(寺尾紗穂、講談社現代新書)
⑪ 9.23『日本軍兵士―アジア太平洋戦争の現実』(吉田裕、中公新書)
⑫ 11.11『原民喜―死と愛と孤独の肖像』(梯久美子、岩波新書)
⑬ 2019.1.20 『トランプのアメリカに住む』(吉見俊哉、岩波新書)
⑭ 3.17『宝島』(真藤順丈、講談社)
⑮ 4.20『82年生まれ キム・ジヨン』(チョナムジュ、筑摩書房)
⑯ 6.1 『アマゾンの倉庫で絶望し、ウーバーの車で発狂した』(ジェームス・ブラッドワース、光文社)
⑰ 7.6 『呪いの言葉の解き方』(上西充子、晶文社)
⑱ 8.24『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(ブレィディみかこ、新潮文庫)
⑲ 11.10 『人間の経済』(宇沢弘文、新潮新書)
⑳ 2020.1.25 『小国主義―日本の近代を読みなおす』(田中彰、岩波新書)
*3.2 『熱源』(川越宗一、文春文庫)を予定したがコロナ蔓延のために開催できず。それまでの会場神保町の喫茶店を諦め、以後オンライン開催とし、現在に至る。
㉑ 2020.6.27『武器としての「資本論」』(白井聰、東洋経済新報社)
㉒ 8.1 『給食の歴史』(藤原辰史、岩波新書)
㉓ 9.26『つながりの経済をつくる』(工藤律子、岩波書店)
㉔ 10.31『人新世の「資本論」』(斎藤幸平、集英社新書)
㉕ 12.19『民衆暴力』(藤野裕子、中公新書)
㉖2021.1.30『海をあげる』(上間陽子、筑摩書房)
㉗ 2.27『3・11後の社会運動』(樋口直人・松谷満、筑摩選書)
㉘ 4.24『縁食論―孤食と共食のあいだ』(藤原辰史、ミシマ社)
㉙ 6.6『労働組合とは何か』(木下武男、岩波新書)
㉚ 7.17『追想美術館』(志真斗美恵、績文堂出版)
㉛ 9.18『他社の靴を履くーアナーキックエンパシーのすすめ』(ブレィディみかこ、文芸春秋社)
㉜ 11.6『デジタルファシズム』(堤未果、N H K出版新書)
㉝ 12.18『貧困パンデミック』(稲葉剛、明石書店)
㉞ 2022.2.12 『日本移民日記』(MOMENT JOON、岩波書店)
㉟ 4.2『〈万人〉から離れて立つ表現―貝原浩の戯画を読む』(太田昌国、藤田印刷エクセレントブックス)
㊱ 6.4『忘却の野に春を想う』(姜信子・山内明美、白水社)
㊲ 8.7『朝日新聞政治部』(鮫島浩、講談社)
㊳ 10.1 『死刑について』(平野啓一郎、岩波書店)
㊴ 12.3 『中学生から知りたい ウクライナのこと』(小山哲・藤原辰史、ミシマ社)
㊵ 2023.2.4 (未定)
●第39回読書会 : 『中学生から知りたい ウクライナのこと』(12/3)報告

12月3日(日)第39回ブッククラブ読書会が開かれました。取り上げた本は『中学生から 知りたい ウクライナのこと』(小山哲・藤原辰史、ミシマ社)。参加者は9人でした。 ウクライナでの戦争をめぐり運動内部でも討論の難しい状態にあることが、まず指摘さ れた。メディアの劣化に加え、現場の実情をみるとすでに風化さえ始まっている。その点 で著者・藤原辰史さんの対話的思考、あるいは対話能力に学びたい。また「ロシアの過ち は我々の過ちでもある。ロシアにとって侵略しないという選択肢はあったことをまず指摘 したい。その上でプーチンあるいはゼレンスキーを主語として語るのではなく、民衆を主 語にしない限り戦争を止められない」。さらに軍産複合体の実態をもっと暴く必要がある 。本書には「マイダン革命」前後の現代史への言及が不足していて、その時点でのNATOの 動向も合わせみることが必要ではないかとの意見もあった。 この日の『東京新聞』には「敵基地攻撃能力を保有する」ことで法改正することを自公 両党が合意したとの報道がされている。ウクライナでの戦争を理由付けに軍備増強=戦争 準備が進んでいる。本書で強調されている「歴史を忘れない執念」がぜひ必要になる。 総じて民衆の立場から歴史をどう見るかを改めて考えさせる本であり、ウクライナの歴 史と現実に即して戦争と平和の緊迫したいまを捉える好著との感想だった。 ▷次回は2月4日(土)午後2時開始。オンラインとリアル(ビデオプレス事務所)とのハ イブリッドで行います。 取り上げる本は決まり次第ご案内します。推薦があればどうぞ投稿してください。(しま)
●第38回読書会 : 平野啓一郎『死刑について』(10/1)報告

「憎しみ」の共同体から「優しさ」の共同体へ
困難な道だがともに歩みたい 10月1日開催されたレイバーブッククラブ第38回読書会は、平野啓一郎著『死刑 について』(岩波書店)を取り上げました。参加者は11人でした。 本書は、2019年12月に大阪弁護士会が、2021年10月に日本弁護士連合会が主催し た講演会・シンポジウムでの著者の講演をもとに加筆・再構成したもの。それだ けにとても読みやすく、よどみなく一気に読み終えられる本です。 とはいえ、内容は深く、真摯な思考がめぐらされていて、ずしりと重い読後感が 残ります。読書会冒頭のひと言感想では、「死刑存置派だった平野さんが実体験 を踏まえて死刑廃止論に転換していった過程が自然で、好感が持てた」「なぜ死 刑がなくならないのかを考えることで日本という国の姿も浮き彫りになる、とい う問題提起を受けとめたい」「戦後の人権教育の失敗が死刑支持につながってい るとの指摘は大いに賛成」などの発言がありました。 議論は続きます。「暴力は相手を力でねじ伏せて自分の言うことを通してしま う。戦争と死刑とは密接に関係している。人間にとって重たい課題」「なぜ人を 殺してはいけないのか。改悛しない殺人犯であっても死刑にしてはいけない、と 言えるのか。平野さんの答えは『基本的人権を保障した憲法があるから』。これ はすごく大事なこと」「加害者の立場になって考えるというのは、ブレイディみ かこさんの“他者の靴を履く”“エンパシー”と通じる」「たとえ憲法がなくても、 人が生きること、どんな命も大切にする。それはこの社会が優しいか優しくない かの分かれ目」… 「命のかけがえのなさを思う。それは加害者も同じ。人間の尊厳を考えると、殺 してしまったらおしまい、二度とない」という発言に関連して、チャットで、 「個人の尊重、生命への権利」を定めた日本国憲法13条は「公共の福祉に反しな い限り」との条件付きなのに対し、大韓民国憲法やスイス連邦基本法の同様の条 文には一切条件が付いていない、という重要な指摘も寄せられました。 どのようにすれば死刑をめぐって理性的な議論を深め、死刑廃止へと近づいてい けるのか。死刑に関する世界の趨勢などさまざまなデータをきちんと伝えるこ と、死刑執行の実態とくに絞首刑の残虐さを知らせること(大阪弁護士会制作の ビデオ「絞首刑を考える」がYouTubeで見られます:https://www.youtube.com /watch?v=wD4x8LcmKy8 )が必要でしょう。被害者のケア、被害者の苦しみに徹 底して寄り添うこと、被害者を救済する制度づくりも不可欠です。被害者遺族と 死刑囚が直接面と向かって話をする場を設けたらどうか、遺族にとって「ゆる し」のきっかけになるかもしれない、という提案もありました。 報告者の特権として、この本で私が一番感動した個所を引用させてください。 70~71ページ、あなたが殺されて、あの世から残された家族を見守っているとし たら、というところです。家族の周りにただ犯人への「憎しみ」にだけ共感する 人たちが集まっているのが見えたとして、それは本当に喜ばしいことだろうか、 と平野さんは問い、こう自答します。--せっかく一度しかない人生なのだか ら、もっと楽しいこと、心安らぐこと、美しいものに触れること、何もかも忘れ て好きな人と一緒にいること、……そんな時間の使い方をしてほしいとは願わない でしょうか? そして、そのための手助けをしてくれる人たちが集まって、優し く気づかってくれるとするなら、それは憎しみの連帯よりも望ましいことではな いでしょうか。-- 朝日新聞や朝日新聞デジタルに死刑制度に関する記事が載り、NNNドキュメン ト'22で「飯塚事件」のことが放送されたこともあり、タイムリーな読書会とな りました。(浅井健治) *次回は12月3日(土)14時~を予定しています。取り上げる本は未定です。
●第37回読書会 : 『朝日新聞政治部』(8/7)報告
8月7日(日)第37回ブッククラブ読書会が開かれました。 取り上げた本は『朝日新聞政治部』(鮫島浩、講談社)。
参加者は13人、初めての参加 者が3人で編集担当者も参加されました。(報告=志真秀弘) 主な発言を紹介しましょう。 「『朝日』の舞台裏、知る記者も描かれ興味深い」「著者の情熱的な筆力に惹きつけられ た」「特に前半だが著者の自慢話にきこえ、著者夫人の指摘する著者の『傲慢』を感ずる 」「中扉裏の販売部数をみると全紙が凋落しているのにはやはり驚く」「新聞退潮の原因 は著者のいうネットの拡大、驕りからくる旧態依然の記事などに加え、非正規の増大によ る若い読者層の変容など多面的にある」「市民・市民運動に呼応する積極的姿勢こそ『朝 日』を救うはず」「吉田調書は誤報にあらずとの声が当時の運動内にもあった」「〈アリ の一言〉の『調査報道をあらためて復活・強化し、権力と正面から対峙し追及することこ そ新聞の生き残る道』との本書への意見も聞くべき」など活発な発言が続きました。編集 担当者からは「当初は新書版でのメディア論を依頼したところ、出来上がった原稿は重量 のある思いの丈のこもったもので、急遽厚表紙単行本に切り替えた」経過、さらに述べら れた意見への考えなどが話されました。 さらに内部の記者活動の可能性、地方新聞の中には見るべき反権力の姿勢がある。自立 したネットメディアのこれからなど話題は尽きず。 この読書会は、いま社会に求められる討論の「場」を創る試みでもあると思うとの声も あり、それぞれの「読み」を聞くにとどまらない有意義な時間を過ごしました。 ▷次回は10月1日(土)午後2時開始。これまでどおりオンラインで行います。 取り上げる本は決まり次第ご案内します。推薦があればどうぞ投稿してください。 ▷出発時は神田神保町のブックカフェで読書会を開いていました。気軽に全国どこからで も参加できるオンラインに加え、直接話せる会を早く復活させたいものです。
●第36回読書会 : 『忘却の野に春を想う』(6/4)報告〜パワフルな二人から飛び出す石の飛礫
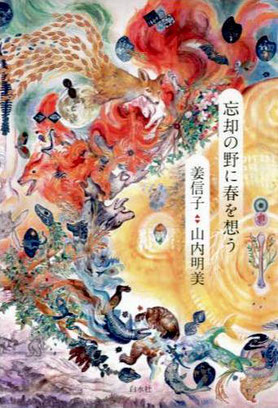
今回の本は、『忘却の野に春を想う』(白水社、2022年)で、先ずこの魅力的なタイトルに惹きつけられた。著者は、姜信子(きょう・のぶこ)と山内明美(やまうち・あけみ)。2018年12月から2年間に渡る二人の往復書簡である。女性二人の往復書簡と聞くと、日々の暮らしのなかでの思いを随筆風に綴ったものかとの思われる向きもあろうが、これがどうしてどうして、パワフルな二人から飛び出す石の飛礫が、明治以来150年の日本の近代の歩みに大きな穴を穿とうとする野心的な告発の書なのである。
「奪われた野にも春は来るのだろうか」と題する姜の第一信から始まる。姜は、コメ難民として植民地朝鮮から日本に渡ってきた祖父母をもつ在日3世であり、自らを「近代日本最初の難民の一族の子であり、奪われたままの存在なのだ」と位置づける。一方の山内は、『こども東北学』などの著書もある歴史社会学の研究者で、宮城教育大学で教鞭をとる。南三陸のコメ農家に生まれ育ち、東北の農村のフィールドワークを続けるなかで、3.11.も体験し、「東北は内なる植民地なのだ」との思いを深める。そうか、二人は、「コメ」と「植民地」をめぐる問題意識で深く共鳴し、共に闘う同志なのだ、と納得する。土に根ざし、命の源を育んできた民の土地を、近代化の大波が襲い、収奪し、自然環境もろとも破壊してゆく。
二人の視点は当然ながら東北に留まらす、アイヌ民族の暮らした土地へ、足尾鉱毒事件、そして水俣、辺野古へと連なり、150年の時空を行き交う。「近代社会は、勝者と敗者、加害者と被害者を生む、しかし両者は二項対立でなく、敗者も、勝者を真ん中に置いた仕組みの中に再配置されて、抗いようもなく近代社会の無力な共犯者となる。」と姜は語る。この痛切な認識が、姜に、「国家とか民族とか、強力な求心力で人を括っていくすべての共同体から逃れること。(…)周縁から無数の想像力で無数の穴(=中心)を穿ち、中心という概念を無化していく闘い。(…)近代を越えてゆく私なりの<もうひとつの世>を呼び出したい」と語らせる。
一方、山内は「近代を包み込んでも余りある世界」を考えたいという。その道程で二人は、縁(よすが)としてさまざまな人物に言及し、その世界観を探る。宮沢賢治、安藤昌益、アナキストの金子文子などなど。そして何よりも誰よりも、その存在に導かれるように繰り返し登場するのは、石牟礼道子である。「近代の業と罰」を一身に引き受けてしまったような水俣病患者の悲惨を、そして言葉を失った彼らの魂の内なる声を、石牟礼は『苦海浄土』に描き切った、と私は思う。「水俣病事件では、日本資本主義がさらなる苛酷度をもって繁栄の名のもとに食い尽くすものは、もはや直接個人のいのちそのものであることを、わたしたちは知る。」と石牟礼は語った。(『苦海浄土』あとがき)
この2年間に私たちは、コロナパンデミックの襲来があり、その最中に、復興五輪と銘打った東京オリンピックも強行されるというトンチンカンも味わされた。この日本社会はどこまで頽廃と自滅の道を歩み続けるのだろうか。福島の原発事故から10年目の春が巡って来た。山内は、福島の原発事故を「もう一つの敗戦」と呼んだ。奪われた福島の野に春は来るのだろうかという問いは、忘却にゆだねることなく、未来への警告としても反芻し続けねばならないだろう。
ブッククラブでは、バックグラウンドもさまざまな人たちが集い、一冊の本を肴に自由闊達な意見交換ができるのが楽しい。今回は土曜の午後という他のイベントも多いなかで参加者は6名と少なめだったが、次回はまたどんな本が俎上に載るか、多くの参加者との出会いも楽しみである。(内藤洋子)
*次回は8月7日(日)14時、の予定。本は未定です。
●第35回読書会 : 〈万人〉から離れて立つ表現―貝原浩の戯画を読 む

4月2日(土)午後2時から第35回〈ブッククラブ 〉読書会がオンラインで開かれました。参加者は11人(欠席連絡をいただいた方は2人)。取りあげた本は『〈万人〉から離れて立つ表現―貝原浩の戯画を読む』(太田昌国、藤田印刷エクセレントブックス)です。
当日は著者の太田昌国さんにも参加いただいて、いつに増して活気ある討論が展開されました。本書に掲載された戯画は1980年代前半から2005年までに描かれたものです。中曽根から小泉に至る時代の権力者たちが風刺を効かせて活写され、ユーモアで包む表現に皆共通して感心しました。
著者はこの戯画を単に説明するのではなく、自身の状況観・時代観を基礎に鋭い批評を展開しています。なかでも著者の天皇制批判をめぐる論点に共感の意見が多く出されました。また貝原戯画のユーモアを孕む表現の可能性にも討論は及びました。著者は貝原の戯画は「対象の憎々しさにとどまらない、哀れさまで浮かぶ」描写であることを指摘。文章の世界でも言葉をいくら過激にしても人の心にはとどかない。笑いも重要な課題で、たとえば永井愛の演劇世界なども一つの参考として、ユーモアを込めた文章表現の可能性をさらに考えたいとの著者の発言も印象に残りました。
また政治主義に陥らないためには社会総体、そして生活の幅全体に及ぶような批判のあり方を常に大切にしたいという言葉―静かで謙虚な語り口とともに、それは著者の批評を貫く鉄則のように響きました。
●次回読書会は6月4日(土)午後2時オンラインで開会します。
テキストは『忘却の野に春を想う』(姜信子・山内明美、白水社、2200円)です。本書は『ごく普通の在日韓国人』はじめ多数の著作のある姜(1961年生)と宮城県南三陸町に生まれ現在・宮城教育大准教授の山内(1976年生)との幾つもの主題をめぐる往復書簡で構成されています。詳細は改めてご案内します。(志真秀弘)
<第35回読書会案内>

レイバーブッククラブ第35回読書会は『〈万人〉から離れて立つ表現―貝原浩の戯画を読む』(太田昌国)をとりあげます。今回は著者も参加します。
◯日時:4月2日(土)午後2時から4時まで。全員オンライン参加とします。
◯テキストは『〈万人〉から離れて立つ表現―貝原浩の戯画を読む』(太田昌国、藤田印刷エクセレントブックス、2021年12月刊、900円)です。
著者は、レイバーネットのサイトにコラム「太田昌国のサザンクロス」を連載中です。本書は「絵師・貝原浩」(1947-2005)の風刺画=戯画のうち主に1980年代から2005年に貝原が亡くなる直前までの25年間の作品の展示会に際しての、著者太田の講演をまとめたもの。貝原浩の社会風俗から国際政治に至る戯画をみたことのある人は多いでしょうが、著者は画を微細に読み、丁寧に解き明かしていきます。戯画を楽しみ、現代史を知り、著者の鋭い批評に接するーいくつもの味わいを得られる本書を読んで、著者とともに討論しましょう。ぜひご参加ください。
◯参加要領
①参加希望の方は、開会前日までに必ず「〇〇です。ブッククラブに参加します」と書い
て下記あてメール送信してください。
mgg01231@nifty.com
②申し込みいただいた方には、開催前にあらかじめ案内メールを差し上げます。
●第34回読書会 : 日本社会の閉鎖性と差別性『日本移民日記』

2月12日(土)午後2時から第34回〈レイバーブッククラブ〉読書会(オンライン)が開かれました。参加者は13人で、取りあげた本は『日本移民日記』(MOMENT JOON、岩波書店)。
冒頭、著者のプロフィールが紹介された。ソウル育ちの30歳で、大阪大学大学院に在籍しラッパーとして活躍中。2年間の軍隊生活時にその抑圧に耐えられず自殺未遂に追い込まれたが大学に戻る。日本は移民を認めていないが、彼は自身を「移民」だとして日本で生活している「いろいろなことを考えさせられた」ことが読後感として共通に語られた。日本社会の閉鎖性、差別性が著者の日常生活を通して浮き彫りになっていく。そして彼のラップを聴いた人は「ヒリヒリしていて」聞き通せないようなインパクトを感じたという。他方『金曜日』(2/11)に書評を執筆した秋原京さんは、「自分は34歳の在日4世」だが、この本の与えてくれる発見と同時に著者との間の距離感も感じたと語った。エリートでありニューカマーであるMOMENTさんと依然として差別にさらされて生きる「在日」の仲間たちとの距離を考えさせられた。他面、福島からの移住者を映像で追い続ける堀切さとみさんは、本書の「移民」生活の感覚に移住を余儀なくされた人たちとの共通性を感じたという。また入管政策などの反動性をみると憲法は無くなってしまったかのようで、政治はますます悪くなっているとの意見も聞かれた。
同時に、日本社会の変化をもたらしてきた先人の闘いへの感謝を忘れないというMOMENTさんの言葉に、感動を覚えるとの感想もあり、討論は時間を延長して続いた。「差別語」を意図的にラップで使うことの意味など取り上げられなかった論点も多くあった。(志真秀弘)
▷次回は4月2日(土)午後2時開会でオンライン使用とします。取り上げる本は後日連絡します。
●第33回読書会 『貧困パンデミック』(稲葉剛)
12月18日(土)午後2時から第33回〈ブッククラブ〉読書会が開かれました。参加者は7人(欠席連絡をいただいた方が6人)で、取りあげた本は『貧困パンデミックー寝ている「公助」を叩き起こす』(稲葉剛、明石書店)。
著者は、すでに30年近く路上生活者を中心に生活困窮者支援に取り組む。つくろい東京ファンドの代表理事として、文字通り「地べたから」活動している。その姿勢に参加者の誰もがうたれた。「住まいは基本的人権」と主張して住まいの保障を運動の最重要課題としていることも大事な要点で、参加者みんなその通りとの意見だった。本書の活動の様子(2020年3月―2021年5月)から貧困の実情もよくわかる。「生活保護」を認定させるとき、まず行政に家族に連絡するのをやめさせる、加えて当事者の抵抗感を除くなどが重要な一歩であることがよくわかる。また「女性、非正規、外国人」などに強いしわ寄せがいく現実、窓口を担当する自治体職員も「官製ワーキングプア」にされ疲弊が著しい実態なども討議で指摘された。
さらに瀬戸大作さん(『新型コロナ災害緊急アクション活動日誌 2020・4―2021・3』著者)の活動がソウルの市民活動の実践を学んでいること、「私には帰る場所がない 家を失う女性たち」(NHKクローズアップ現代+)の文字起こしが番組サイトで読めることなども紹介された。他方支援活動自体の財政も困難で、メンバーも足りない。その支援も大切なことなど議論は広がった。
次回は2月12日(土)午後2時開会でやはりオンラインです。取り上げる本は改めてご案内します。当日も何冊か挙げられましたが、さらにメール等で案をお寄せください。(志真秀弘)
●第32回読書会 『デジタル・ファシズム』(堤未果)

11月6日(土)午後2時から第32回〈ブッククラブ 〉読書会が開かれた。参加者は初参加の方を含め11人で、取りあげた本は『デジタル・ファシズムー日本の資産と主権が消える』(堤未果、NHK出版新書)だった。
『デジタル・ファシズム』は、行政、金融そして教育、それぞれの分野での「デジタル化」の問題点が的確にまとめられ、警鐘が鳴らしている本として参加者の評価は高かった。討論で、行政と教育の現場で今何が進行しているかの実態が多く語られた。デジタル庁の発足はこれからデジタル化を進めるのではなく、各省庁にバラバラになっている個人データを一気に統合して行こうとするもの。
教育現場では生徒一人一人の成績、学校生活、健康状態・素行・家庭環境などがデジタル庁に集約される。ボストンコンサルティング、NEC、ベネッセなどがこれに深く関わっているが、発足反対の運動は政党レベルはもちろん市民運動も極めて弱かった。学校現場の教育労働者も疲弊させられ自主的な教材作りなどの時間が奪われている。他面生活の中でデジタル化に少しでも抵抗できることはないだろうか、あるいは利便性に巻き込まれてなし崩しに公共性が破壊される状態にどう歯止めをかけるかなどの議論も活発に進んだ。
35年教員をしてきた愛知の小野政美さんは、「子どもは悩んで躓きながら成長する。それに寄り添うのが教師だった。ケンカしたり言い争ったりすることが大事だが、デジタル教育でいっさいなくなる。いま医者は患者を見ずにPC画面をにらめっこしているが、教員も同じことになる。とても危険なことだ。教員組合はこういう問題にこそ取り組むべきだ。ただ過労死寸前まで働かせられて余裕のない職場実態がある」と熱く語ってくれた。
次回は12月18日(土)午後2時開会でやはりオンラインです。取り上げる本は改めてご案内します。(志真秀弘)
●第31回読書会 ブレイディみかこ『他者の靴を履く』

9月18日(土)第31回レイバーブッククラブ読書会がオンラインで開かれました。取り上げた本は『他者の靴を履く-アナーキック・エンパシーのすすめ』(ブレイディみかこ、文藝春秋)です。参加者は11人でした。
参加者に共通する意見は「これまでのアナキズムへの理解が一新された、あるいは深まった」です。エンパシー(他者の立場に立って物事を考える力)を多面的に追求する展開のなかでアナキズムの重要性、とくに相互扶助はじめ民主主義の思想が根幹だと著者が主張することにみなが共感し、さらにこれまでの社会主義を目指す運動内部に民主主義論が未発達だったのではないかとの意見も加わり本書の民主主義論も注目されました。
著者のエンパシー理解は、負の側面も含めてのもので正鵠を得たものであり、たとえばアダム・スミスの『道徳情操論』を「上手にこえた」とさえ思うとの評価もきかれました。
他面、著者はマスコミに登場する機会も増え、保育士の生活と労働から離れていることへの危惧もあるとの意見には、本書を読む限りその心配はなさそうだとの感想がありました。プチブルジョワジーへの著者の評価への疑問なども出されるなど、豊富な内容に惹かれての活発な討論のひとときでした。
読書会の醍醐味であるいろいろな人の「読み」を聞くことができ、楽しい時間でした。
次回は11月6日(土)午後2時開始で、これまでどおりオンラインで行います。取り上げる本は決まり次第ご案内します。推薦があればどうぞ投稿してください。(志真秀弘)
●第30回読書会『追想美術館』筆者交えてディスカッション

7月17日に行われたブッククラブ第30回の報告です。
今回は『追想美術館』(志真斗美恵著、績文堂出版)が取り上げられました。オンライン開催で参加者は12名。筆者の志真斗美恵さんを交えて、常連のメンバーに新参加者2名が加わり多彩でした。いつもとは一味違う芸術分野の選本に新鮮な驚き、感想が印象的でした。
ケーテ・コルヴィッツを初め、べん・シャーン、セバスチャン・サルガド、粟津潔、石垣栄太郎ら、民衆の側に立った画家・芸術家の人と作品をていねいに描いた本書を評価する感想が相次ぎました。まず、装丁が親しみやすく読みやすい。タイトルも良くできている。世の中を変えていくという姿勢が全編つらぬかれている。直接作品と対峙し、自分の目、自分の言葉で表現しているのがいい。気軽に読み始めたが、ズシンと重いテーマ。現在を射抜く視点がある。時代を超えて民衆を励ます芸術の力を感じた等々。本書で唯一批判的な視点で取り上げられた藤田嗣治と戦争画については、作品の評価と作家の評価は別に考えるべきではないかとの意見もありました。
筆者の志真斗美恵さんは「今回の出版で多くの人から感想を寄せてもらった。一番の思いは芸術運動の力を伝えたいこと」と語りました。本書にあるように、ケーテの版画がスメドレーから魯迅へ、そして日本へとつながっていくさまは、まさに芸術運動の力。レイバーネットの原点のスローガン「文化のないたたかいなんてありえない」をあらためて想起しました。(佐々木有美)
※次回は9月18日14:00~16:00 あらためてご案内します。
●第29回読書会『労働組合とは何か』示唆に富む議論

6月6日(日)開催のブッククラブ第29回読書会報告です。 今回は『労働組合とは何か』(木下武男、岩波新書)が取り上げられた。参加者は14人で 労働運動の第一線で活躍中の方も参加し、議論は組合運動の活動家に一石を投じようとの 著者の意欲に応えるような充実したものになった。
本書は、はじめに中世のギルドまで遡って労働組合誕生の歴史を探り、さらにイギリスそ してアメリカの運動史を辿っている。その記述は鮮やかであり、また日本の組合運動が、 組織的な特性もあって企業に抱え込まれてしまいやすいとの指摘も的確なものとの意見で 一致した。他面、欧米の歴史篇が現在まで届いていないのは残念であり、また企業別労働 組合を「あだ花」とする見方には異論も出された。現実にねざし、課題に取り組んできた 歴史から学ぶこともまた多いのではないか、また労働法制を実際に活用する必要性にも言 及して欲しかったとの意見もあった。討論はそれぞれの実践経験も踏まえて、意見が率直 に出され、さらに本書の提起に触発されて今日的な課題を考える方向へと展開した。非正規あるいは「雇用類似」労働の組織化は国際的な課題と言っていいが、20代、30代の労働 者が置かれた労働環境は、想像を越えて過酷である。反面それにへこたれない若い人も現れ始めている。たとえば最近の入管法改悪反対運動の短時間での広がりを見ると、組合運 動の視点や枠組みにとらわれないで考えていけば可能性も見えてくるのではないかとの意 見も聞かれた。
気迫ある本書に促されるように、示唆に富む議論が展開された2時間でし た。(志真秀弘)
◯次回は7月17日(土)を予定し、詳しくは後日ご案内します。
●第28回読書会『縁食論』これからの共同(体)を考える

28回読書会は4月24日(土)午後2時から4時までオンラインで開かれました。テキストは『縁食論―孤食と共食のあいだ』(藤原達史、ミシマ社)。参加者は15 人で愛知、広島に加えて、新しく大分、京都、新潟の方が加わりました。コロナのためにやむなくオンラインに切り替えたのですが、そのおかげで参加者は全国に広がりました。
感想を全員が語ることから会は始まりました。わかりやすく柔らかい語りで一気に読めたというのが共通していて、「縁食」を媒介にこれからの共同(体)を考えてみようとの著者の問題提起もそれぞれに受け止められたようです。 同時に食べものをつくる人たちの視点も考えたい、あるいは縁食を広げようとする時に突き当たるだろう実情なども指摘されました。
子ども食堂や炊き出しに関わっている Oさんは、食べる人とつくる人との線引きはなかなか崩れないこと、そして生活保護を必要としてもそれを忌避する人もいる実情に似て、子ども食堂でも本当に必要としている人が実はなかなか来ない実態にあると。給食調理の場で働くHさんは、著者の現状への強い怒りを感じた。食べものを無料にして商品化を止めるなどの問題提起は現状を変えるための想像力が必要だとの訴えだと感じました。一方給食がなくなると、昼食が食べられなくなる子どもいて、一斉休校時に一食 38円のカップラーメンを大量に買って、子どもに与えてしのぐ母親もいるのが実情です。そんな論議に給食を地域に開く可能性を考えられないかとの意見もありました。
「縁食」をめぐる著者の問題提起から実際の問題点へと討論は展開しました。縁側のもたらす豊かな広がりがかつて存在したが、そうした過去を媒介に未来のあり方は見えてこないか、などの議論も続きました。 この本は、論文調ではなく随想的スタイルをあえてとって問題提起を発し、読む人の柔軟な思考を促そうとしていました。それが2時間ノンストップで参加者全員から活発な意見が聞かれた所以だったかもしれません。
著者の「藤原」の読みは「ふじはら」が正しいこと、初参加のMさんは著者と小中学校とも同窓だったなどのエピソードも紹介され、いくつもの「縁」を感じた会でもありました。 次回は6月6日(日)を予定しています。詳細は後日ご案内します。
→次回詳細はこちら
●第27回読書会『3.11後の社会運動』全国から16人が参加

志真秀弘です。
レイバーブッククラブ読書会の報告をします。
27回読書会は2月27日(土)午後2時からオンラインで開かれました。テキストは『3・11後の社会運動-8万人のデータからわかったこと』(樋口直人・松谷満、筑摩書房)。参加者は16人。新しい方が3人加わり、主題の「デモ」のことから今の社会状況に至るまで活発な議論が広がりました。参加者は首都圏以外に広島、岡山、愛知、静岡などに広がりました。オンライの効用です。オンラインでの討論も、回数を重ねることでスムースになってきました。この本は参加者の小野政美さんの紹介でしたが、研究者の活動と活動家の活動との接点を、この読書会で創れたかなと思います。特に「孤立し、細分化され、序列化された社会状況」が当日の議論の焦点のひとつになりました。なお本書は以下でも紹介しています。↓
『本の発見』192回 http://www.labornetjp.org/news/2021/hon192
●次回28回は、やはりオンラインで4月24日(土)2時開始です。取り上げる本は『縁食論―孤食と共食のあいだ』(藤原辰史、ミシマ社、1870円、2020年11月刊)。著者の本は前に『給食の歴史』を取り上げています。彼は今精力的に仕事をし、発言している若い歴史学者です。この本は、「一人出版社」で意欲的な活動を続けているミシマ社刊ということもあり注目です。ぜひご参加ください。
●第26回読書会『海をあげる』この本と出会えてよかった

1月30日(土)午後2時からオンラインで、レイバーブッククラブ第26回読書会が開かれました。テキストは『海をあげる』(上間陽子、筑摩書房)。参加者は13人で、新しい方が4人加わり、熱のこもった発言が続きました。本書は「週刊本の発見」128回(1/28・佐々木有美)↓でも取り上げられています。http://www.labornetjp.org/news/2021/hon189
冒頭に、「欠席するが、この本と出会えてよかった」との浅井健治さんからのメッセージも伝えられ、参加者一同、同感した。 著者の静かだが深い語り口は、みんなに届いていて、問いかけの重さにたじろいだとの声もあった。前作『裸足で逃げるー沖縄の夜の街の少女たち』の刊行から 本作に至る年月のなかに、「聞く力」を含め研究者である著者自身が試されていく過程が あっただろうし、そこに著者の本領があるのではないか。話を聞いた少女の手術に立ち会 い、精神科医の診察に同行し、それこそ伴走するような著者の努力・生き方に聞くことの 重さが感じられる。沖縄戦の歴史と沖縄に生きることは暴力と向き合うことに他ならない 現実が、浮き彫りにされる。さらに本書の内容を体現するような装丁、表現に適した余白 を充分とった組み方などにも話は及んだ。本書 推薦者の植松青児さんは「ここなら、この本を受け止めてもらえると予感した」が、それ は当たったと語ったが、時間いっぱい全員が感想を述べあい、充実した時間を創ることが できた。
●次回27回は、やはりオンラインで2月27日(土)2時開始です。取り上げる本は『3・11後の社会運動-8万人のデータからわかったこと』 (樋口直人・松谷満、筑摩書房、1650円、2020年6月刊)。3・11後、各地に広がった反原発運動、さらに安保法制反対運動もこれをひ きつぐように広がりをみせた。そこに立ち上がったのはどのような人たちだったか、その動機は何かを読みとく。これからを考えることのできる本です。ぜひご参加ください。(志真秀弘)
●第25回読書会『民衆暴力』ー近代日本の歴史をめぐり討論

12月19日(土)午後2時からオンラインで、ブッククラブの第25回読書会が開かれました。テキストは『民衆暴力―一揆、暴動、虐殺の日本近代』(藤野裕子)。参加者は11名で、新しい方は3名。オンラインの効用でしょうか、このところ海外(韓国)を含めて各地からの参加があり、討論もはずみました。
本書について、自らは記録を残すことがない人々の実像を、資料の正確な読み込みを通じて明らかにしていく、歴史家のたしかな視点が感じられる労作だ、というのが参加者の一致した感想。同時に「権力に向けた暴力と被差別者に対する暴力の両方を直視し、それらを同時に理解していく力」(本書はしがき)の必要を受け止め、近代日本の歴史をめぐり、参加者の積極的な発言が続いた。
参加者のひとり小野政美さん(元愛知県小学校教員、〈ひのきみ全国ネット〉代表)は、愛知トリエンナーレ「表現の不自由展」の経験を振り返りながら、河村たかし市長たちが「天皇陛下を侮辱している、従軍慰安婦はいなかった」などと煽っていたが、これら行政・民間の有力者に「右翼」と言えない多勢の普通の人たちが世代を越えて呼応し、展示に圧力をかけてきた。「歴史修正主義が行政にまで入り 込んでいる」(あとがき)ことをこの体験からも実感したと語った。またメディアに流される危険が広がってきている問題、日本の近代化の中で形成されたナショナリズムと現在動きの問題など議論は広がった。
次回26回は、やはりオンラインで年明け2021年1月30日(土)2時開始です。取り上げる本は『海をあげる』(上間陽子、筑摩書房、1760円、2020年10月刊)。普天間基地近くに住む著者は、今未成年の少女たちの支援・調査に携わっていて、これは初めてのエッセイ集とのこと。「何も言わずに読んでほしい。ここにある言葉を、ただただ読んでほしい。」(作家・柴崎友香)。ぜひご参加ください。 (報告=志真秀弘)
★案内 : 2020.10.31『人新世の「資本論」』(斎藤幸平)

ブッククラブの次回(24回)読書会は10月31日(土曜日)午後2時開会。とり上げるのは『人新世の「資本論」』です。
◯日時:10月31日(土)午後2時から4時まで 全員オンライン参加とし、Zoomを使います。
☆テキストは『人新世の「資本論」』(斎藤幸平、集英社新書、2020年9月、1020円)。
地球規模の危機をもたらした新自由主義=現代資本主義はどのようにして変えることがで きるか?本書は、この問いに正面から応える意欲作です。最晩年のマルクスの研究を通し ての、言わば〈マルクス再考〉の作業が新鮮な問題提起につながります。若い著者による 既成概念を打ち破る主張は、すでに活発な議論を呼んでいるようです。ぜひご参加くださ い。
◯参加要領 ①参加希望の方は、開会前日の明日までに必ず「〇〇です。ブッククラブに参加します」 と書いて下記あてメール送信してください。 mgg01231@nifty.ne.jp
②申し込みいただいた方には、開催前にあらかじめ案内メールを差し上げます。
●『人新世の「資本論」』読書会の報告
10月31日(土)午後2時からオンラインで、ブッククラブの第24回読書会が開かれました。テキストは『人新世の「資本論」』(斎藤幸平)。参加者は12名で、そのうち初めての方が5名おられました。
今進行している気候変動の危機をもたらしている究極の要因は資本主義にあるという本書の主張は参加者全員が共感し、加えて著者のデータの的確な読み込みによって極めて説得的との共通した意見でした。例えば1989年ソ連崩壊後の30年間に人類は化石燃料の半分を消費したとの数字は、環境危機がどれほど切迫したものかを示します。一方、晩年のマルクスは「生産力至上主義」「ヨーロッパ中心主義」を克服してコミュニズムの可能性をさらに広げたという著者の主張については、参加者の意見は分かれました。それは「脱成長コミュニズム」の提唱に結びつく重要な論点でもあり、実際運動(例えば韓国の運動など)への目配りと合わせて、さらに展開が求められる点かもしれません。同時に労働者協同組合はじめ、いくつもの実例紹介などから、著者は、気候変動を食い止め資本主義を変える社会運動の現実性を捉えようとしています。そうした点を含め、いまの言論状況にあって傑出した問題提起に違いないとの意見で一致しました。
今回の議論をとおして、本書の論点の豊富さを改めて教えられた気がしています。
次回25回はやはりオンラインで12月19日(土)2時開始です。取り上げる本は『民衆暴力―一揆・暴動・虐殺の日本近代』(藤野裕子、中公新書、820円)。労作であり、意欲作です。ぜひご参加ください。(しま)
●報告 : 2020.9.26『つながりの経済を創る―スペイン発「もうひとつの世界」への道』

佐々木です。ようやく秋らしくなってきました。以下、ブッククラブの報告です。
9月26日、「レイバーブッククラブ」が、オンラインで開催されました。参加者は7人。今回は、工藤律子著『つながりの経済を創る―スペイン発「もうひとつの世界」への道』(岩波書店)を取り上げました。2011年5月15日の大市民デモから始まったスペイン社会の変革。それは時間銀行や労働者協同組合など、新自由主義(資本主義)の人間切り捨てとは180度異なった、人間のつながりを大切にする経済社会の構築でした。移民・難民やお年寄り、障がい者も支援されるだけでなく、自分の力を発揮できるしくみ。足元の変革から世界を変えようとする人々は、政党を作り、行政を巻き込み、暮らしを具体的に変えてきました。
ディスカッションは盛り上がり、以下のような意見が出されました。「著者の謙虚に学ぶ姿勢に好感をもった。助け合い文化を取り戻すことが必要。コロナ後のあるべき社会を示している」「おもしろかった。生協活動と重なる部分があった。人間は人とのつながりの中でエネルギーがわいてくる」「現実に実践しているのがすばらしい。日本は遅れている。様々な活動はヒントに満ちている」「1930年代のスペイン革命の中に、こうした活動の原型がある。連帯経済の試みは現在の日本でも行われている」「励まされた。写真がすばらしい。対抗社会のイメージが明らかになった。」
次回の予定は、10月31日(土)午後2時~ 斎藤幸平さんの注目の新刊『人新世の「資本論」』です。また、あらためてご案内します。
●報告 : 2020.8.1 藤原辰史『給食の歴史』めぐって討論

レイバーブッククラブの例会は、2020年8月1日にオンラインで開催されました。10人が参加しました。取り上げたのは、藤原辰史氏の『給食の歴史』(岩波新書、2018年)とネットで話題になった「パンデミックを生きる指針」(B面の岩波新書)でした。会には現役の給食調理員も参加し、さまざまな角度からディスカッションが行われました。岡山県から参加した森健一さんが、以下、感想を寄せてくれました。なお次回例会は、9月26日(土)午後2時〜オンラインで行います。詳細後日。(ブッククラブ事務局)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●藤原辰史『給食の歴史』合評会に参加して 森 健一
私が同書を読み、コメントしたいのは、次のことでした。一つは、1965年6月、『毎日新聞』の「山形県のへき地校に完全給食を」の声に、首相の佐藤栄作〔1901年~75年〕が「このような問題こそわれわれの考えるべきことだ」と応じている箇所です(176頁)。佐藤栄作は、同年「沖縄の祖国復帰が実現しない限り、わが国の戦後は終わらない」と那覇空港で演説しているのですが、全国の津々浦々で何が起きているのかを配慮し、保守政治家として心を砕く「度量」がなお、あったと思うのです。
ところが、今日、首相の安倍晋三が、2月末、「3月2日から春休み」にと全国一斉休校をいきなり求めたことに対し、首相官邸はもとより、文科省の次官も全国の教育委員会も反対せず、これに粛々と従ったことです。学校が急に休みになれば、学校給食が唯一のバランスよい栄養ある食事という子どもや家庭では学習が困難な子ども、新型コロナウイルスとは隔てられている離島や山間地の学校の子ども・・、彼らの目には浮かんでいないのだと思いました(政治家、官僚、学校関係者も劣化・・)。
松原明氏も、霞が関、厚労省の官僚らに要請に行っても、端正なスーツで固めた彼らには、多くの国民が、生活の端々でどういう境遇、状態にあるのか、およそ想像が出来ていないな、と痛感するそうです。彼らの多くは、中・高一貫のエリート私学にあって、公立中学などで様々な生活背景をもつ子どもと遊び、交流して、社会を身で知る機会を持たなかったと思います。
テーマの「給食」は、ともに同じ食事をとることで「人としての平等」をじかに知る場でもある訳です。もう一つは、合評のなかで、吉田裕『日本軍兵士』(中公新書、2017年)を引いて、日本軍は、歯科を軽視していて、将兵らはせいぜい「正(征)露丸」(クレオソート)を詰めるくらいで、虫歯に悩んだとの叙述が、この合評会で紹介されたことでした。
私は出典を忘れたのですが、歴史的に米(海)軍は歯科を重視していて、歯科の専門部隊があり、将兵の口腔(こうくう)衛生に特に配慮している。これは、戦後、学校給食を置き土産にした、GHQの医官で准将のクロウフォード・サムス(1902年~94年)が、軍隊として占領統治の遂行のためにと、学校給食を重視したこと(93頁)にも通じます。きわめて合理的な訳です。ところが、今日、武漢に由来すると言われる、新型コロナ禍によって、世界最強の米第7艦隊(中国を見据えた西太平洋に展開)が機能不全に陥って、トランプ政権は有効な対応策をとれないでいる。きわめて象徴的だと思います。
最後ですが、2016年夏、連合鹿児島ユニオンとして福岡や大分のユニオンと共に、韓国・ソウルの民主労総本部を訪問、交流しました。「韓国の学校給食は日本により良い」と聞き、給食のありようは、時々の階級関係、民衆の力量により進みもするし、後退もすると実感しました。国政や地方政治を変えて、学校給食を良くすることは、子どもの貧困問題にどれほど私たちが取り組めているのかの指標になるのだと思います。
★レイバーネット事務局
173-0036 東京都板橋区向原2-22-17-108
Tel 03-3530-8588 Fax 03-3530-8578